今回の記事では、交通事故加害者が自己破産した場合の救済手段について、詳しくみていこう。
まずは、自己破産がどのような手続きなのかを、解説していくね。
目次
交通事故加害者が自己破産したら

自己破産はどのような手続か
最初に、自己破産の手続がどのようなものか説明をしておきましょう。
自己破産手続は、
- 破産手続
- 免責手続
の2つに分かれます。
1.の破産手続は、破産者が保有している財産を各債権者に債権額に応じて平等に分配する手続きのことをいいます。
例えば、破産手続では、破産者の保有している不動産を売却して換価し、債権者に分配することなどが行われます。
2.の免責手続は、債権者に破産者の保有している財産を分配しても残っている債務について、法律上、支払義務をなくすことをいいます。
つまりは、破産者の負っている債務を免責する(チャラにする)手続のことです。
皆さんの話題にのぼる自己破産というと、2.免責手続のことを指すことが多いと思います。
ここでも、自己破産のうち、2.免責手続のことを念頭に話を進めていきます。
免責債権と非免責債権
自己破産の免責手続において破産者の負っている債務が免責されるという話をしましたが、正確には、免責される債権(免責債権)と免責されない債権(非免責債権)とがあります。
破産法では、非免責債権が定められていて、非免責債権以外は免責債権とされています。
非免責債権は、次の債権のことをいいます。
- 租税等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 婚姻費用、養育費等の扶養義務に係る請求権
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- 罰金等の請求権
交通事故の損害賠償請求権との関係では、
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
に該当するかが問題になることがあります。
しかしながら、bでいう悪意は、故意を超えた害意のことを指しており、交通事故において、このような悪意が認められることは、ほぼないといっていいでしょう。
また、加害者に故意や重大な過失が認められることも、ほとんどなく、多くの交通事故に基づく損害賠償請求権は、免責債権となっています。
非免責債権となる交通事故に基づく損害賠償請求権とはどのようなものがあるか
破産法では、b破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権とc故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権と定められています。
ですので、cの場合、物損は対象となりません。
つまり、車両やバイク等が壊れた物損については、bの悪意がない限り、必ず免責されます。
次に、故意又は重大な過失についてですが、例えば、酒酔い運転、無免許運転、危険運転過失致死傷罪の適用のある交通事故が挙げられます。
なお、故意行為による事故を交通事故と呼ぶかは別として、自動車を使って故意に人をひき殺したという場合の損害賠償請求権は、bでいう悪意が認められて、非免責債権に当たるものと考えられます。
交通事故加害者が自己破産した場合の対処法は

交通事故後に自己破産手続きを開始し、免責されてしまった場合には、裁判で争う事になるよ。
破産手続開始決定日を確認する
自己破産における免責手続の対象となる債権債務は、破産手続開始決定日を基準とします。
破産手続開始決定日において存在していた損害賠償請求権(破産手続開始決定日前に発生した交通事故に係る損害賠償請求権)は、免責債権となる可能性が出てくるのに対し、破産手続開始決定日後に発生した損害賠償請求権(破産手続開始決定日後に発生した交通事故に係る損害賠償請求権)は、破産手続の影響を受けません。
破産手続の影響を受けないということは、交通事故の被害者は、加害者に対し、問題なく損害賠償請求できるということになります。
ですので、加害者が自己破産したという話を聞いたときは、破産手続開始決定日を確認し、交通事故の前なのか、後なのかを確認しておくと良いでしょう。
損害賠償請求訴訟
自己破産をした加害者は、任意に、被害者からの損害賠償請求に応じる可能性は低いと思われます。
加害者としては、免責されたと思っているのですから、無理もないように思われます。
では、結局、免責債権か非免責債権かというのは、どのような状況で確定するのでしょうか。
答えは、被害者の加害者に対する損害賠償請求訴訟です。
損害賠償請求訴訟において、裁判官が、損害賠償請求権が免責債権なのか(被害者の損害賠償請求を認めない)、非免責債権なのか(被害者の損害賠償請求を認める)を判断するということになります。
場合によっては、被害者は、損害賠償請求訴訟を提起して、免責債権か非免責債権かを争うということになります。
加害者が自己破産した場合の被害者の救済手段
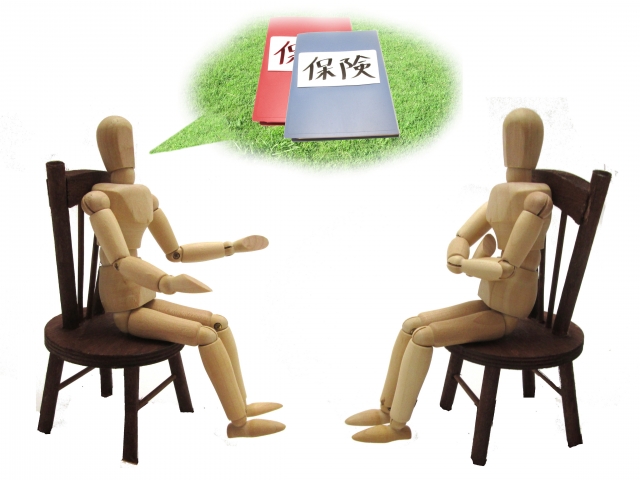
どちらにも加入していない場合には、政府保障事業を活用しよう。
自分の加入している保険内容をチェックしてみるのも良いね。
自賠責
加害者が自賠責保険に加入している場合、加害者が自己破産をしたとしても、被害者は、自動車損害賠償保障法16条によって、自賠責保険会社に対して、直接に、保険金請求をすることができます。
ですので、仮に、加害者が自己破産をしてしまったとしても、加害者が自賠責保険に加入していれば、被害者者は、自賠責保険の定める保険金については、受け取ることができます。
なお、自賠責保険は、人身損害のみを対象としていることや保険金の基準が定められていることには注意してください。
任意保険
多くの損害保険会社は、約款において、加害者(任意保険からすれば契約者)が破産した場合において、被害者が任意保険会社に対して、直接、保険金請求できることを認めています。
ですので、仮に、加害者が自己破産をしてしまったとしても、加害者が任意保険に加入していれば、被害者は、任意保険会社に対して、保険金請求をすることができます。
対人対物無制限の保険の場合、被害者は、交通事故で被った全損害について補填してもらえる可能性があります。
なお、加害者が死亡して、加害者の相続人が全員相続放棄をした場合にも、自己破産の場合と同様、多くの任意保険の約款で、被害者の任意保険会社に対する直接請求が認められています。
政府保障事業
加害者が、自賠責保険すら入っていない無保険者で、さらに、自己破産までしてしまった場合はどうでしょうか。
そのような場合は、政府保障事業を利用することができます。
政府保障事業は、保険金の基準は、自賠責保険と同様です。
ただ、仮渡金の制度がない、社会保障の利用が前提となる等、自賠責保険と異なる部分もあります。
自分の加入している保険
被害者自身が加入している保険を利用して損害の補填を図るという方法もあり得るところです。
例えば、
- 無保険者傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- 人身傷害保険
など、加害者から損害賠償を受けられなかった場合でも、利用できる保険を確認してみることをお勧めします。
交通事故に基づく損害賠償請求権で非免責債権となった事例

免責されるのか、非免責債権となるのかは、裁判により、重過失かどうかを判断する事になるんだよ。
交通事故に基づく損害賠償請求権が非免責債権となった裁判例は、ほとんどありません。
しかしながら、東京地方裁判所平成28年11月30日判決があります。
同判決は、自転車事故に関する事例ではありますが、
「重過失とは、一般に、故意に比肩する程度に重い過失であると解されており、被告の理解は概ねこれを容れうるものと解されるが、前記1において認めたとおり、被告は、本件事故当時、被告車である自転車を、薄暗い自転車の通行可能な歩行者優先歩道上を、時速約25kmから30kmという原動機付自転車の法定最高速度程度の危険な速度で走行させつつ、無灯火の上、進路前方左右の歩行者等の有無及びその安全の確認を懈怠していたものであるから、本件事故に係る被告の過失は、故意に比肩する程度に重い過失であって、被告の理解を前提としても、重過失と認めるのが相当である。したがって、本件事故により生じた原告の被告に対する損害賠償請求権が、本件免責許可決定に基づき免責されることはない。」
と判示しています。
内容を確認すると、具体的な状況や過失の程度等を考慮して、重過失か否かを認定しています。
阿部栄一郎
早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年東京弁護士会登録。
交通事故、不動産、離婚、相続など幅広い案件を担当するほか、顧問弁護士として企業法務も手がける。ソフトな人当たりと、的確なアドバイスで依頼者からの信頼も厚い。交通事故では、被害者加害者双方の案件の担当経験を持つ。(所属事務所プロフィールページ)
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故の加害者・被害者には、誰でもなり得るものです。しかしながら、誰もが適切に交通事故の示談交渉をできるわけではありません。一般の人は、主婦が休業損害を貰えることや適切な慰謝料額の算定方法が分からないかもしれません。ましてや、紛争処理センターや訴訟の対応などは経験のない人の方が多いと思います。保険会社との対応が精神的に辛いとおっしゃる方もいます。
不足している知識の補充、加害者側との対応や訴訟等の対応で頼りになるのが弁護士です。相談でもいいですし、ちょっとした疑問の解消のためでもいいです。事務対応や精神的負担の軽減のためでもいいですので、交通事故に遭ったら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。






